

投稿日:
心のキャッチボール
~円滑なコミュニケーションを目指して~
冒頭から告白ですが、いまだに私は対人コミュニケーションが苦手です。以前は考えてもみなかったのですが、どうやら上手ではないことがわかりました。心理学やコミュニケーション学などを学ぶ過程で、恥ずかしながら判明した事実です。私が参加した学びの場には、明らかに対人コミュニケーションに悩みがあり、解決したいと思っている人が多かったのですが、私のようにコミュニケーションの能力問題について後々気づく稀有な人もいらっしゃると思います。自分の告白を交えて対人コミュニケーションに関して、コラムに書きたいと思います。
相互理解の必要性
私の場合は、「どうしてわかってくれないんだろう」と思うことが多く、説得や指摘事項において誤解が生じたり、意見交換の場では、即座に自分の真意を上手く伝えられなかったり、もどかしさを感じていました。ここまで書くと皆さまは気づかれたかもしれませんが、私は”自分が期待した通りに相手が理解していない。理解すべき”という相手の責任ばかり問うことが多く、伝える/伝えきる努力をしていなかったのです。そもそもコミュニケーションは成立しておらず、まさにone-wayコミュニケーションです。またこのような期待や相手の責任を問うことばかりだったので、自分の予測と異なる意見交換になった時は、真意を伝える力や柔軟に対応する力が育まれていなかったのです。周囲からするといい迷惑です。「この人何言ってるんだろう」「皆考え方は違うし、あなたと同じ考えや価値観を持っている訳じゃない」「押し付けられても迷惑」など、私に関わってくださった皆さんは人間が出来ているので、正面切って指摘されたことは一度もありませんが、密かに思われていたと思います。明らかに自分の意見はOK!(I'm OK!)、理解できないあなたはnot OK!(You’re not OK!)、そういうつもりはなくても事実はこのように誰もHAPPYになれない状態です。
自分のコミュニケーションの傾向に気づいた後は、コーチング、アサーション、交流分析、ビジネスコミュニケーション、人間関係の心理学、家族の心理学などなど手当たり次第に手をつけています。(今でも・・笑)
コミュニケーションとは
そもそも「コミュニケーション」は、下記の(1)~(4)の流れがあって円滑に行われます。
( 1 ) 自己理解 ( 2 ) 他者理解 ( 3 ) 自己表現 ( 4 ) 相互理解
では、この4つについて解説していきます。
( 1 ) 自己理解
先ずコミュニケーションは「自己理解」から始まります。自分のことを知っておかないと他者に向かい合えないからです。 私の場合の自己理解=気づきは、大学の授業のコミュニケーション学の項目で登場するソーシャル・スタイルから始まりました。これは人の性格や内面的要因よりも、人の外側に現れた、直接この目で観察することができる行動そのものに、焦点を当てるものです(接客販売研修で、初めて会うお客さまと友好なコミュニケーションをとるために外観情報が大切。とお話ししているのは、この学問に依るものです)。ソーシャル・スタイルでは、主導型、分析型、友好型 、表出型の4つに分類することができます。詳細の説明はここでは控えますが、是非検索してみて下さい。この4つの内私は「表出型」です。強みは、外交的、情熱的、自発的などが挙げられます。このタイプだと分かった途端、他者から言われて心地よいと感じるもの、感じないものなど、嬉しくなるくらい自分のことに気づくことができましたし、他のグループの人との交流の仕方も明確になりました。自分のことを知るのに時間がかかるんだと気づけたことは嬉しいことで、楽しくもありました。
ですが、コミュニケーションの次の段階の「他者理解」が厄介で、まだまだ修行中です。
( 2 ) 他者理解
次の段階の「他者理解」では向かい合う相手のことを知り理解します。 私が試しているのは「アクティブ・リスニング(Active Listening)=積極的傾聴」です。相手の話をおざなりに聞くのではなく、相手が何を感じ、何を考え、何を言わんとするか積極的に聴き、是非善悪の判断をせず、相手の気持ち、欲求をそれとして受け入れ、理解しようとすることを言います。ロジャーズというアメリカの臨床心理学者が提唱したものです。 「積極的傾聴 Active Listening」の方法
<1>共感的理解と受容
善し悪しの評価をせず、あいづちとうなずきをしながらありのままを聴き、理解し、一緒に感じる努力をします。
<2>くりかえす
ある程度聴いた時点で相手の話のポイントを整理して、繰り返し自分の言葉でフィードバックします。聴くスピードの方が話すスピードより5倍ほども速いため、聴き手の方が先走る傾向があるので要注意です。私はこれが苦手で、十分に聴こうという意欲はあるのですが、同意した途端同じような体験を相手に話したくなり、「おしゃべり泥棒」になります。「ごめんなさい。あなたの話を聴くべきなのに、自分の話になってしまって・・」と謝ること、しばしばです。
<3>明確化をする
相手が何となく気づいてはいるものの、まだはっきりとは意識化していない感情や気持ちを、聴き手が言葉に表してフィードバックします。
<4>質問をする
話し手に時折質問をして助け、話をリードしたり、具体的な情報を得ます。
<5>沈黙を待つ
沈黙の間、話し手は表現できないような感情を味わっていたり、自分を見つめなおしているので、考えを邪魔せず、沈黙を待つことがよい聴き手になることにつながります。この点でも私はついつい質問を投げかけてしまい、待ってあげることが苦手です。特にリモートでは、昔の衛星中継のように動画やレスポンスにタイムラグが発生するので、待つのが難しいと痛感しています。それでも、この技法を知って、意識できるようになり、少しずづつ改善ができているように思います。
善し悪しの評価をせず、あいづちとうなずきをしながらありのままを聴き、理解し、一緒に感じる努力をします。
<2>くりかえす
ある程度聴いた時点で相手の話のポイントを整理して、繰り返し自分の言葉でフィードバックします。聴くスピードの方が話すスピードより5倍ほども速いため、聴き手の方が先走る傾向があるので要注意です。私はこれが苦手で、十分に聴こうという意欲はあるのですが、同意した途端同じような体験を相手に話したくなり、「おしゃべり泥棒」になります。「ごめんなさい。あなたの話を聴くべきなのに、自分の話になってしまって・・」と謝ること、しばしばです。
<3>明確化をする
相手が何となく気づいてはいるものの、まだはっきりとは意識化していない感情や気持ちを、聴き手が言葉に表してフィードバックします。
<4>質問をする
話し手に時折質問をして助け、話をリードしたり、具体的な情報を得ます。
<5>沈黙を待つ
沈黙の間、話し手は表現できないような感情を味わっていたり、自分を見つめなおしているので、考えを邪魔せず、沈黙を待つことがよい聴き手になることにつながります。この点でも私はついつい質問を投げかけてしまい、待ってあげることが苦手です。特にリモートでは、昔の衛星中継のように動画やレスポンスにタイムラグが発生するので、待つのが難しいと痛感しています。それでも、この技法を知って、意識できるようになり、少しずづつ改善ができているように思います。
( 3 ) 自己表現
他者と自分自身を尊重し、自分が伝えたいことを伝えていくことになります。この自己表現は(1)自己理解、(2)他者理解、そしてこれから説明する(4)相互理解に少しずつ関与します。( 4 ) 相互理解
やっと終盤本題に入ります。最終段階の「相互理解」ができると、円滑なコミュニケーションになります。「相互理解」を目指すためには、「心のキャッチボール」をしなくてはいけません。「会話のキャッチボール」というのはよく耳にされていると思いますが、対話、交流は、「心」のやりとりです。どこに話し手の意図があるのか?”意図”がボールになるからです。意図のやり取りを続けることがキャッチボールです。コミュニケーションの相手は、性格やプロフィール、キャリア、価値観がさまざまですから、ボールは相手に合わせて投げやすいように受け取ったり、受け取りやすいように投げることが大切です。この「心のキャッチボール」を行うための良策は、「コップの理論」です。対人コミュニケーションを始める以前に、人はそれぞれ価値観という水がいっぱい入っているコップを持っています。満杯状態では、相手を受け入れる余地はありませんよね。したがって、一先ず自分のコップを空にして先に相手の話を聴いて、相手のコップの水を自分のコップに入れます。自分のコップを空にするといっても、自分の価値観の水を捨てるのではなく、一旦別の器に移しておくのです。次に自分のコップの水を相手のコップに注ぎ、自分の感情や考えを伝えます(「積極的自己主張」)。この水の移動は「聴く」「話す」で行われ、相手の立場に立ち、尊重し合い、繰り返す努力が共通性・共有性を相互に作り上げ、このステップこそが相互理解のコミュニケーションになるのです。新鮮な水の授受、きっと楽しいと思います。
お問い合わせ
株式会社三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ
営業統括部 教育事業担当
お電話でのお問い合わせ
050-3150-0074
受付時間:午前10時から午後6時まで
(日曜日および1月1日を除く)
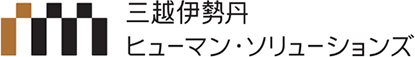
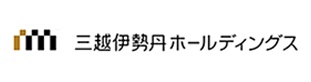


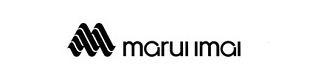





Nishimiyaのひとこと
私自身、随分と勉強したつもりでも相手や状況によって、うまくいったり、いかなかったり、まだまだ不安定ですが、それも味わいながら克服したいと思っています。自分の価値観を一旦別に移すのは勇気がいることだと思いますが、断捨離のように心にスペースができて、気持ちが楽になるかもしれません。お試しください。