

投稿日:
お客さまが行動を変えてくださる伝え方
年末年始、気忙しいのはなぜ?
私が長年夢中になって読み漁っている江戸を舞台にした時代小説には、12月は今でいうところの年度末決算月で、半年から一年分の掛け取りに奔走し、その状況次第でお正月/新年が迎えられるかどうか?というほど切実で大事な時期だったことが描かれています。また現代にも継承されている神社仏閣、公共施設をはじめとした煤払いや大掃除、餅つき、冬至などの慣習、行事もとても多くあります。私見ですが、それら慣習や行事は切実な問題を解決する願掛けのようにさえ思えてきます。また季節を享受しようとする意欲が旺盛で、”気忙しさ”すらも師走につきものと楽しんでいたのかもしれません。余裕がないと言えばそれまでですが、現代人の気忙しさは、コロナ禍、先が見えづらく、人の良識のみに頼る予防策への疲弊などが、苛立ちになりやすいようになっている気がします。「伝えるということ」
顧客接点のある人たちは、「新しい生活様式」によるお客さまへの「お願い」が増えていると思います。そのことによるクレームも耳にすることが増えましたし、先述の気忙しさ、苛立ちからか、お客さまから理不尽な要求や意見もあるようです。皆さまは、どのような「伝え方」「お願いの仕方」をしていますか?苦労されているのは、マスク着用のお願いですか?
アルコール消毒や検温のお願いですか?
並び方、待ち方ですか?
いずれにしても、お客さまの事情、価値観の違いがありお願いの仕方は難しいですね。 今年、様々な機会にお伝えしたノウハウは、「ナッジ理論」を使ったものです。
ナッジ理論とは…?
2017年・ノーベル経済学賞を受賞したリチャード・セイラ-教授が生み出した理論です。ナッジ(nudge)とは、「ヒジで軽く突く(ヒジで突くというささやかなキッカケを与えて人々の行動を変える)」という意味。科学的分析に基づいて人間の行動を変える戦略のことです。
2017年・ノーベル経済学賞を受賞したリチャード・セイラ-教授が生み出した理論です。ナッジ(nudge)とは、「ヒジで軽く突く(ヒジで突くというささやかなキッカケを与えて人々の行動を変える)」という意味。科学的分析に基づいて人間の行動を変える戦略のことです。
有名な事例は、1999年、アムステルダムのスキポール空港で経費削減のため、男子トイレの床の清掃費が高くついていたことから、小便器の内側に一匹のハエの絵を描いた結果、8割もの清掃費が減少したというもの。これは「人は的があると、そこに狙いを定める」という分析に基づき、小便器を正確に利用させたというわけです。ここで「汚さないでください」と注意を促すのではなく、使用者の心理を巧みに利用するナッジによってトイレが綺麗になったのです。日本では、渋谷のスクランブル交差点のDJポリスが有名ですが、生命保険会社、都道府県、市町村の機関の取り組みなどが進んでいます。
では早速、先ほどの理論を実際の接客シーンで考えてみましょう。
いかがでしょうか?
導入例をお読みになって「うちのお店ではつかえないな」と思われた方もいらっしゃると思います。確かにすべての例がお店に相応しいものでないものかもしれません。ここでのポイントは、導入例をもとに皆さまのお店に来店されるお客さまの傾向を考えて、ささやかなキッカケで行動を変えていただけるようなお願いの仕方をしたり、伝え方を工夫したりすることです。今回の例が使えそうなお店の場合でも、お客さまは多様ですから、いくつかの対応例を用意しておくことが良いと思います。 また、そのためには、お客さまに合わせた対応が前提として必要です。これは接客の基本でもありますが、声の大小、話す速度、表現方法などを、お客さまのスピードに合わせているかどうか”ペーシング、マッチング”が重要になってきます。
また飲食店の際、どうしてもお酒が進み、会話が盛り上がってくると、お客さまもついついマスクを付け忘れます。したがって、お願いしたり、お伝えするタイミングも重要です。お料理を提供する時に「冷めないうちが一番美味しいので、集中して召し上がってください」「飲み物のお代わりいかがですか?」「すぐにお持ちしますので、マスクをつけてお待ちくださいませ」と追加確認を普段よりこまめにし、そのタイミングに他の話題とともに、さりげなく行動へのきっかけを作る。というのも一案だと思います。皆さまのアイデアで、気忙しさがふっと忘れられる空間が生まれることを願っています。
お問い合わせ
株式会社三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ
営業統括部 教育事業担当
お電話でのお問い合わせ
050-3150-0074
受付時間:午前10時から午後6時まで
(日曜日および1月1日を除く)
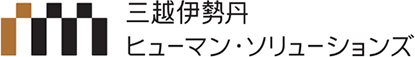
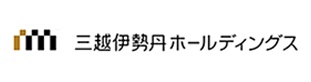


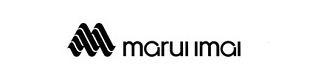





Nishimiyaのひとこと
江戸時代の暮らしは、ゴミのリサイクルやレンタル社会が確立されていて、合理的だったようです。火災が多く、疫病(ウィルス性の病気)も蔓延したり…。それでも生き生きとした暮らしぶりが小説からは伺えます。どうせ生きるなら現実を受け入れ、楽しく生きる。というように、です。現代を生きる私たちも、その精神で他者と交流したいですね。